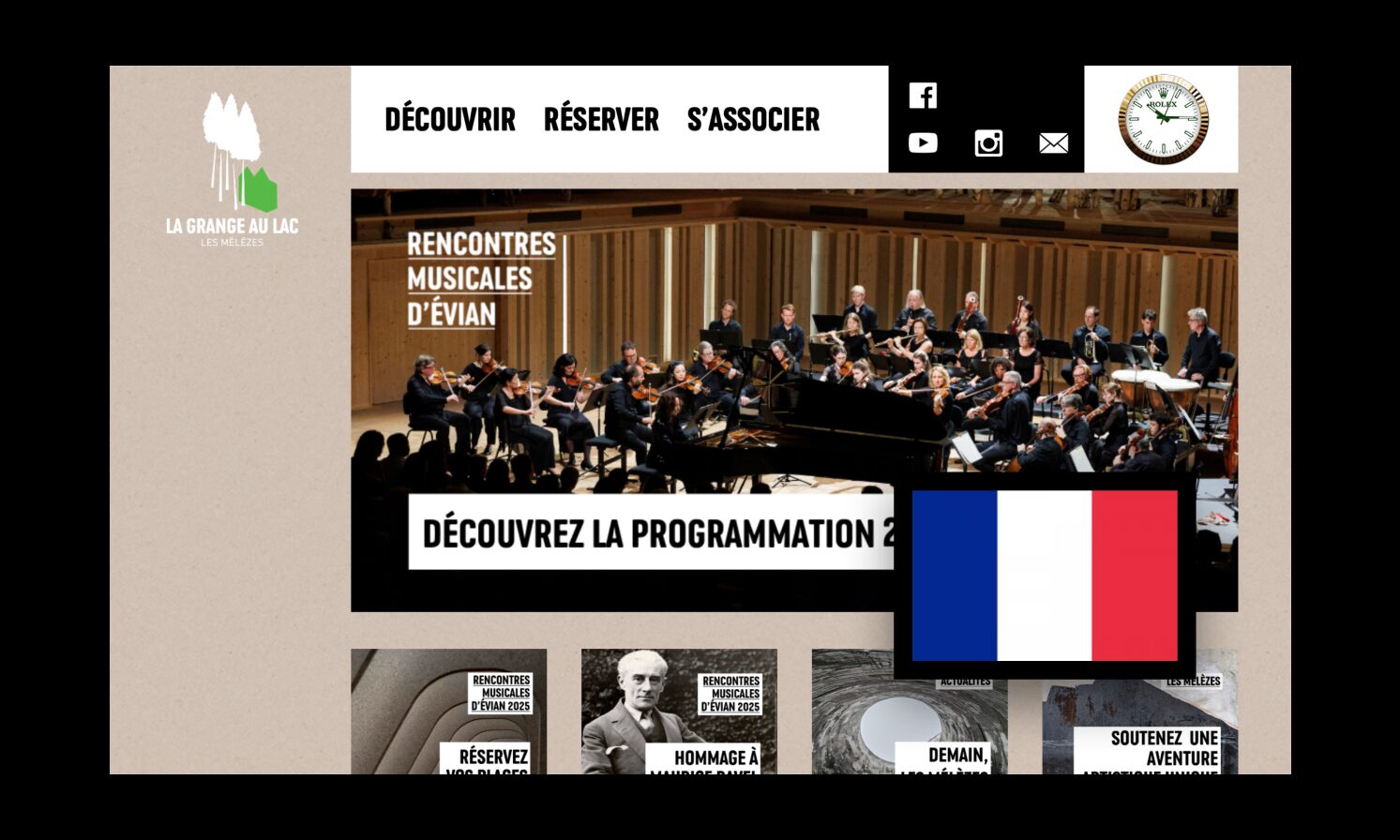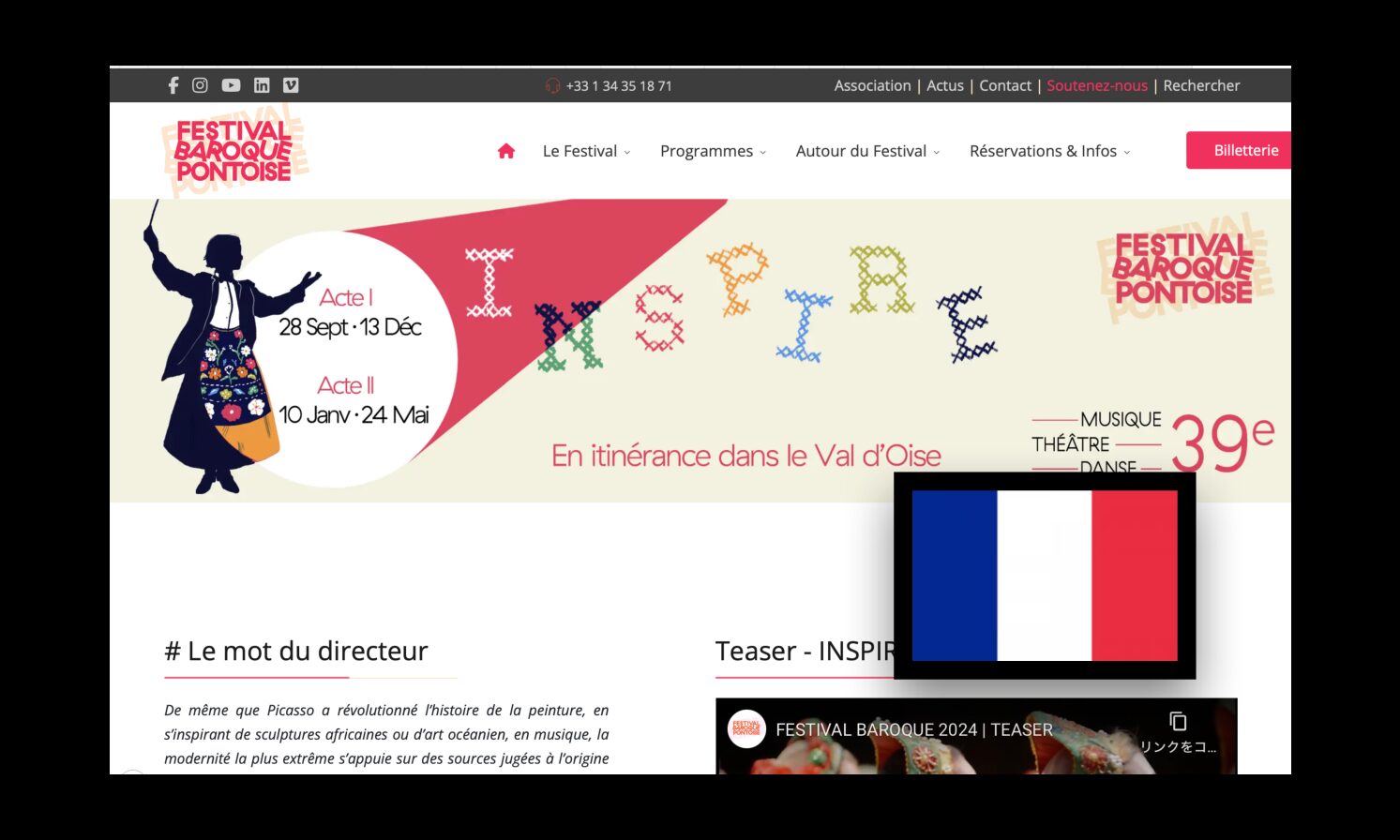ハンス・ロスバウトという指揮者をご存知ですか? 1895年、オーストリア・グラーツの生まれ。グラーツと言えば、日本でも有名な指揮者のカール・ベームとは同郷人ということになる。調べてみたら、ベームは1894年の生まれ。この町は、たった1年違いで、二人も一流指揮者を輩出したことになる。
ロスバウトはどちらかと言えば、シェーンベルクやバルトーク、ストラヴィンスキーといった同時代の作曲家の良き理解者として名をあげた人だ。が、1948年7月にフランスのエクス=アン=プロヴァンス音楽祭の音楽監督に就任。当時、フランスではそれほど広く知られていなかったモーツァルトの大作オペラ《コジ・ファン・トゥッテ》を指揮して大きな成功を得る。
以降、毎年のようにモーツァルトの《ドン・ジョヴァンニ》や《フィガロの結婚》、《後宮からの誘拐》といった歌劇を取り上げ、これは1958年まで続く音楽祭の目玉企画になった。今回取り上げるのは、それらの中で1955年7月に上演された《フィガロの結婚》のライブ録音である。
この音楽祭のオペラ上演は、特設の野外劇場であるアルシュヴェシェ劇場で行われる。そのためか非常に開放的なモーツァルトを聞くことができる。音楽は快適なテンポによるお馴染みの序曲で始まる。本編に入ってもロスバウトの指揮は、余分な誇張やもったいぶったところは皆無で、極めて快調に進む。
レチタティーヴォはチェンバロではなくピアノで伴奏されるが、その乾いた響きは物語を前へ前へと進めていく。また何よりもドイツ語の原語上演にも関わらずお客の反応が素晴らしい。一緒に上演を聞いているような臨場感に満ちていて、聞き手の気分も一気に南仏プロヴァンスに飛んで行く。
配役は女声陣がまず強力。アメリカ出身で非常に気品のある歌を歌うテレサ・シュティヒ=ランダルが伯爵夫人。第2幕・第3幕のアリアは、ともに彼女特有の澄んだ透明な声でしっとりと歌われ、これは全曲の中でいいアクセントになっている。スザンナは当時売り出し中のハイ・ソプラノのリタ・シュトライヒ。テクニックも声も余裕があり、聞いていて非常に気持ちがいい。3幕の手紙の二重唱では、ランダルと二人で極めて美しいデュエットを聞かせている。
後に伯爵夫人も歌うことになるピラール・ローレンガーは、まだここではケルビーノを歌っている。第2幕の「恋とはどんなものかしら」では大きな拍手をもらっている。この3人はいずれもリリックな声で、彼女たちが絡み合う2幕の前半は、まさに美声の饗宴である。
男声陣では、ロランド・パネライが明るく若々しいフィガロを演じていて、貫禄を見せている。これに比べるとハインツ・レーフスは少し軽量級の伯爵に聞こえないでもないが、重唱ではきっちり役目を果たしている。ロスバウトのアプローチは、全体として声楽的・オペラ的というより器楽的・純音楽的であり、そこにこそこの演奏の眼目はあるのである。
《フィガロ》ほどの傑作になると様々なアプローチがあると思うが、ロスバウトと彼の信頼する常連メンバーが作り出す緊密なアンサンブルは、今の耳で聞いても少しも古びて聞こえない。これからもエクス=アン=プロヴァンス音楽祭の創成期を飾る名演として、後世に語り継がれていくに違いない。
amazonでCDを買う ▷
音楽祭プロフィールはこちら ▷
……… アルバム情報
●モーツァルト:歌剧《フィガロの結婚》全曲
ロランド・パネライ(フィガロ)
リタ・シュトライヒ(スザンナ)
ハインツ・レーフス(アルマヴィーヴァ伯爵)
テレサ・シュティヒ=ランダル(伯爵夫人)
ピラール・ローレンガー(ケルビーノ)
クリスティアーネ・ジェラルド(マルツェリーノ)
マルチェッロ・コルティス(バルトロ)
ユグ・キュエノー(ドン・バジリオ)
エクサン・プロヴァンス音楽祭合唱団
パリ音楽院管弦楽団
ハンス・ロスバウト(指揮)
録音方式:モノラル
録音時期:1955年7月、エクス=アン=プロヴァンス音楽祭