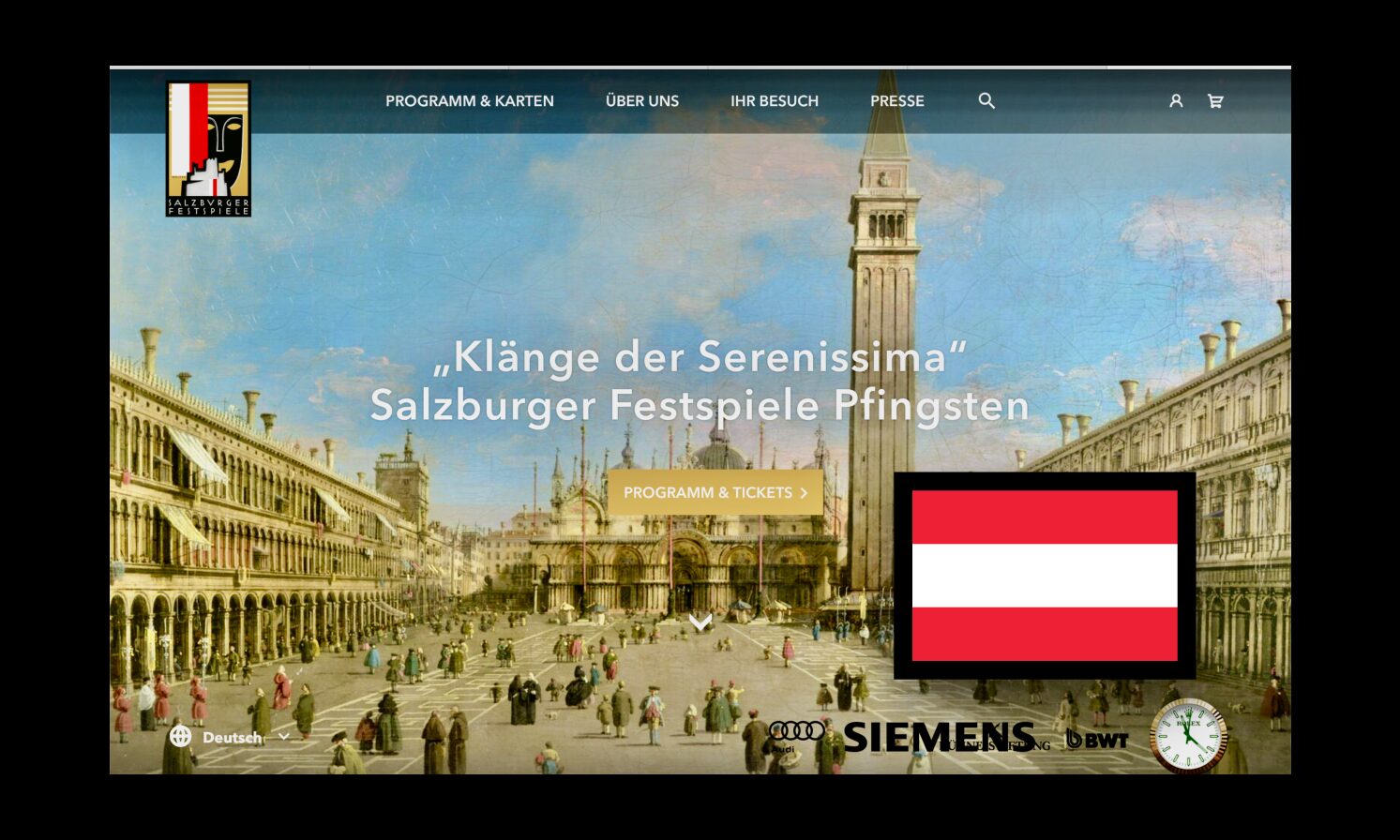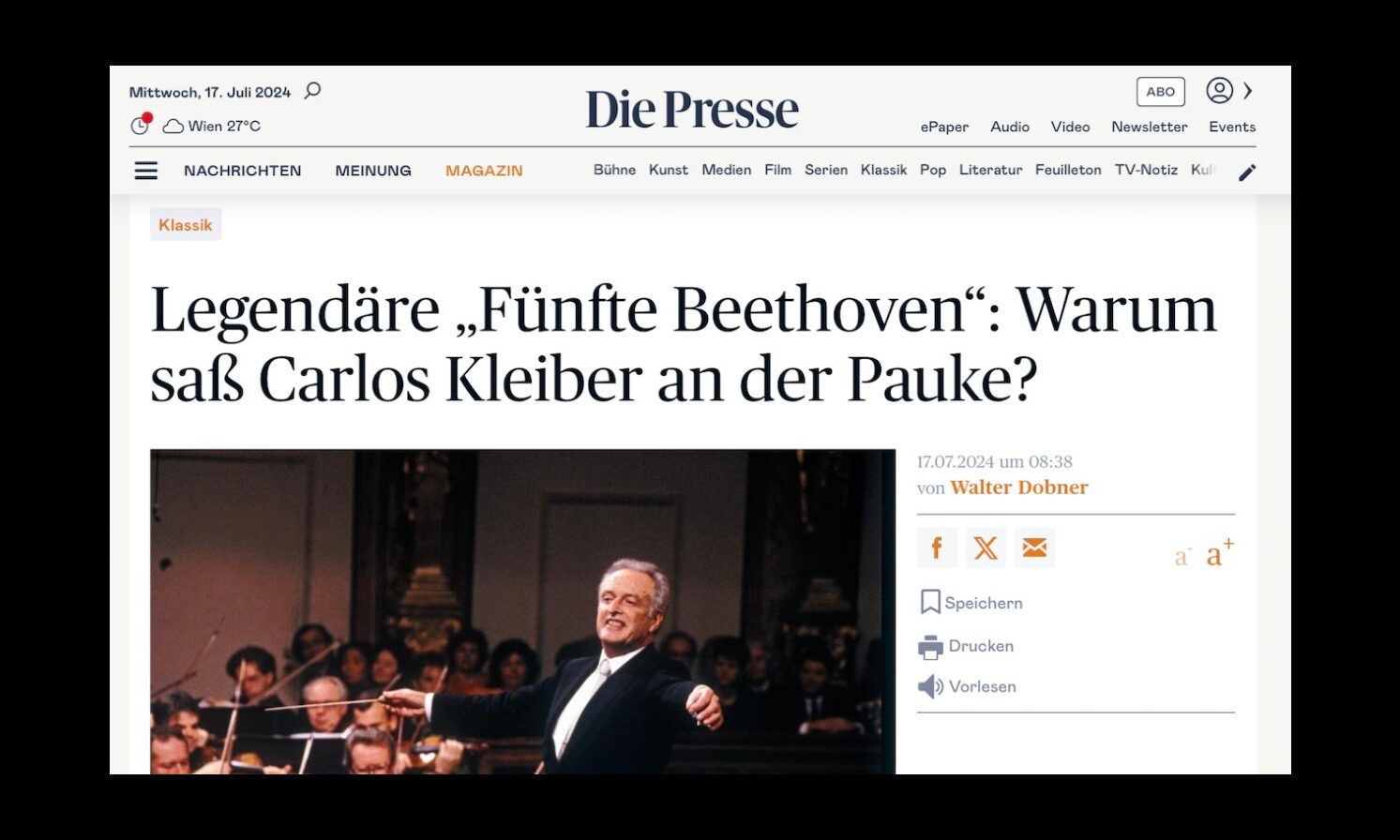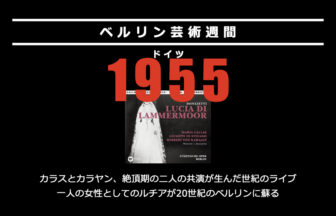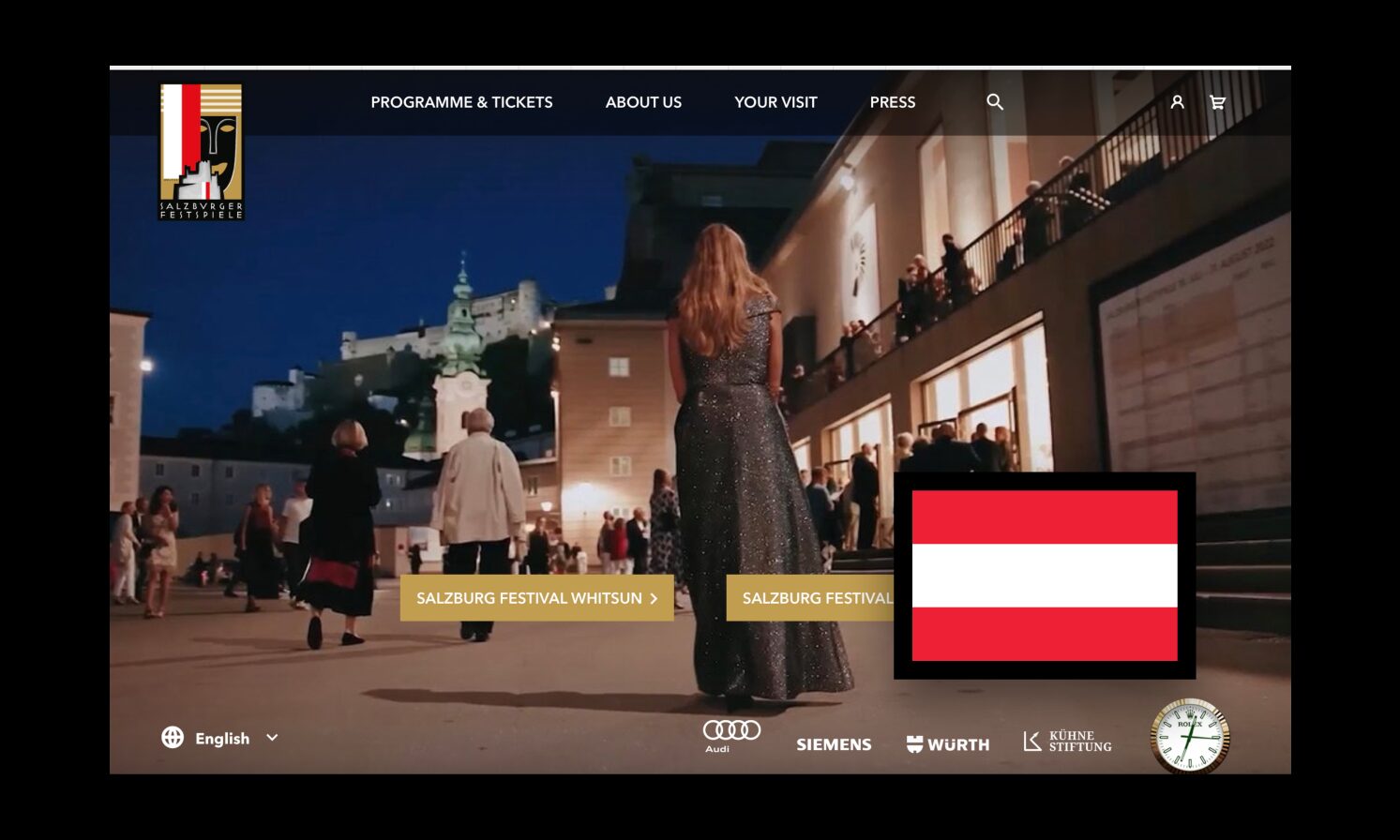グスタフ・マーラー(1860-1911)の手になる長大な交響曲群は、今でこそ世界中のオーケストラにとって日常的なレパートリーになっている。が、それは前世紀の最後の四半世紀以降のこと。その大きな転機になったのが、1967年にウィーン芸術週間の目玉として、コンツェルトハウスで行われた「マーラー・ツィクルス」だった。
「ツィクルス」が行われたのは5月21日から6月18日。その間に12回の演奏会が開かれるという大規模な催しで、しかも、当時すべての公演が我が国でもFM放送でオンエアされたという。
その放送で解説も務めた音楽評論家の吉田秀和は当時、月刊誌『芸術新潮』の連載記事にこう書いている。「ツィクルス」の前年に来日中の指揮者ロリン・マゼールから、深い関係がありながらもマーラーの音楽に馴染みの薄かったウィーンで大規模な「ツィクルス」が行われるという予定を聞いて驚いたと。
……それだけに、私は、一九六六年の秋、ベルリン・ドイツ・オペラの一行が東京に二度目の来日をしにきたとき、ある夕べ、フィッシャー=ディースカウやローリン・マゼールと食事をしながら歓談した折、マゼールの口から、来年はヴィーンの芸術祭(ヴィーンでは五月から六月にかけて開かれる)で、マーラーの全交響曲作品が、つまり交響曲はもちろん、管弦楽伴奏の歌曲のすべてを含む連続演奏会が開かれるという話を聞いて、驚いたのだった。「へえ!ヴィーンでね」「そう、ヴィーンで。」……。
この話からも、“クラシック音楽の本場”ヨーロッパでも極めて珍しい、希少な「ツィクルス」だったことがわかる。当時の資料をみると、顔ぶれも凄い。
1番はジョルジュ・プレートル、2番はレナード・バーンスタイン、3番がハンス・スワロフスキー、4番はヴォルフガング・サヴァリッシュ、5番がショモギ・ラースロー、6番はクラウディオ・アバド、7番はブルーノ・マデルナ、8番はラファエル・クーベリック、9番とクリスタ・ルートヴィヒの独唱で《亡き子を偲ぶ歌》がマゼールだ。加えて、カール・ベームがルートヴィヒと《さすらう若人の歌》、カルロス・クライバーが《大地の歌》、第10番のアダージョと《嘆きの歌》がギュンター・トイリングというのだから。
そこで今回、夏休み企画として、この「ツィクルス」からの録音を2回にわたって紹介したい。まず一つ目は、5月24日に行われた交響曲第6番《悲劇的》の録音で、アバドがウィーン交響楽団を指揮している。彼は2年前、ヘルベルト・フォン・カラヤンからザルツブルク音楽祭に招かれ、やはりマーラーの交響曲第2番《復活》を振って音楽祭デビューを果たしている。アバドにとっては、それに続く大舞台であった。
この時のアバド、後年の超一流オケを振った時のような洗練こそ見られないが、オケをコントロールする力はこの「ツィクルス」の他の演奏以上に強く感じられる。
晩年のアバドの演奏ではアンダンテを第2楽章に置くことになるが、ここではまだスケルツォのまま。この楽章は驚くほど速いテンポで始まるが、その勢いは他ではあまり聴くことができない。アンダンテでの厚い響きも、聴き応えがある。
バーンスタインのように会場を興奮の坩堝に化すようなスケール感こそないが、当時34歳だったアバドの底に秘めた気迫が感じられる好演なのだ。以降、アバドはおよそ3回にわたって交響曲全集を録音するなど、生涯にわたってマーラーの音楽を追及していくことになる。
なお、このアルバムには、ザルツブルク音楽祭の時の《復活》の演奏も同時に収録されている。アバドのその後の活躍の原点を知るという意味でも、貴重な記録となっている。
CDを買う ▷
音楽祭プロフィールはこちら ▷
……… アルバム情報
● マーラー:交響曲第2番《復活》
ステファニア・ヴォイトヴィチ(ソプラノ)
ルクレツィア・ウェスト(アルト)
ウィーン国立歌劇場合唱団
クラウディオ・アバド(指揮)
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
1965年8月14日 / ザルツブルク / ザルツブルク祝祭大劇場(ライヴ)
● マーラー:交響曲第6番《悲劇的》
クラウディオ・アバド(指揮)
ウィーン交響楽団
1967年5月24日 / ウィーン / コンツェルトハウス(ライヴ)