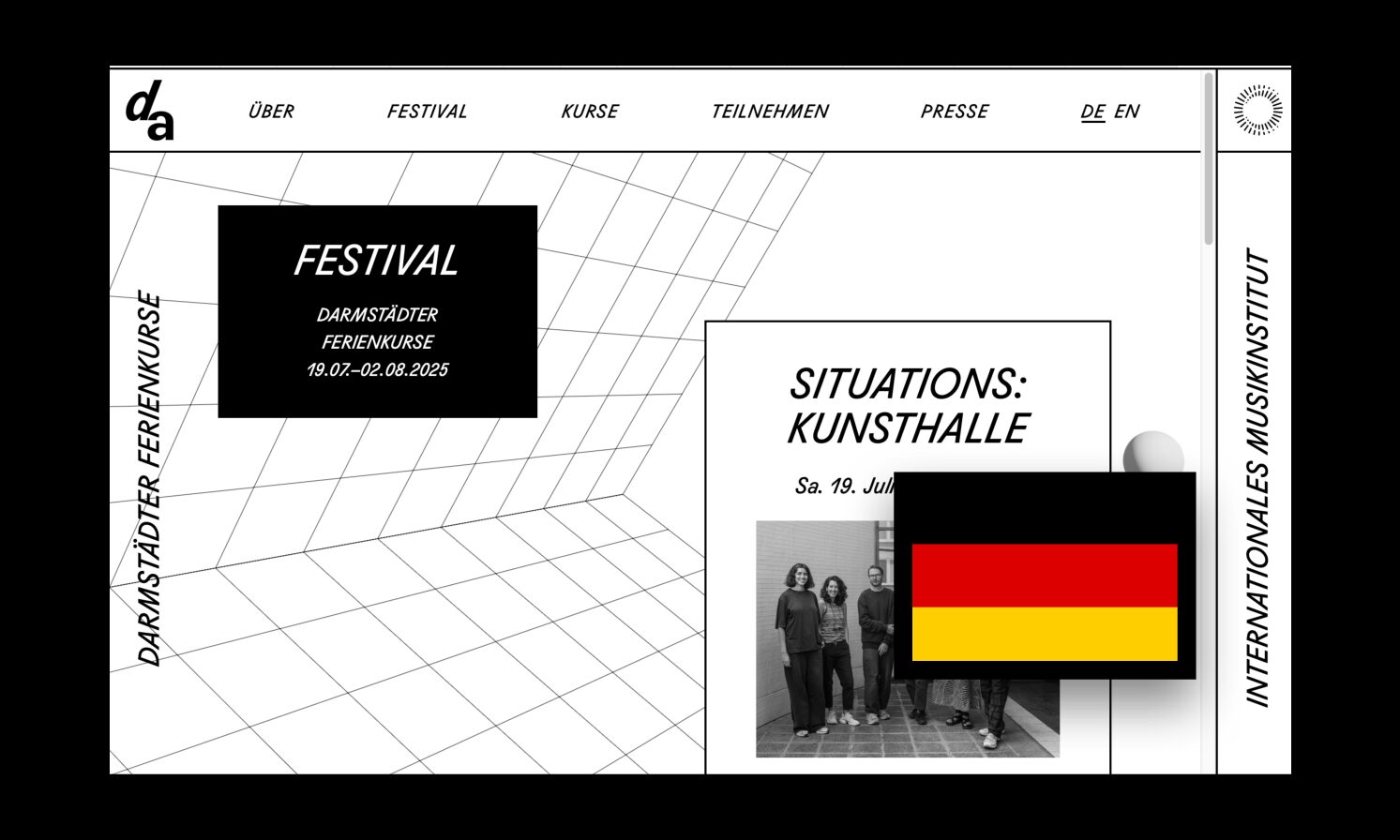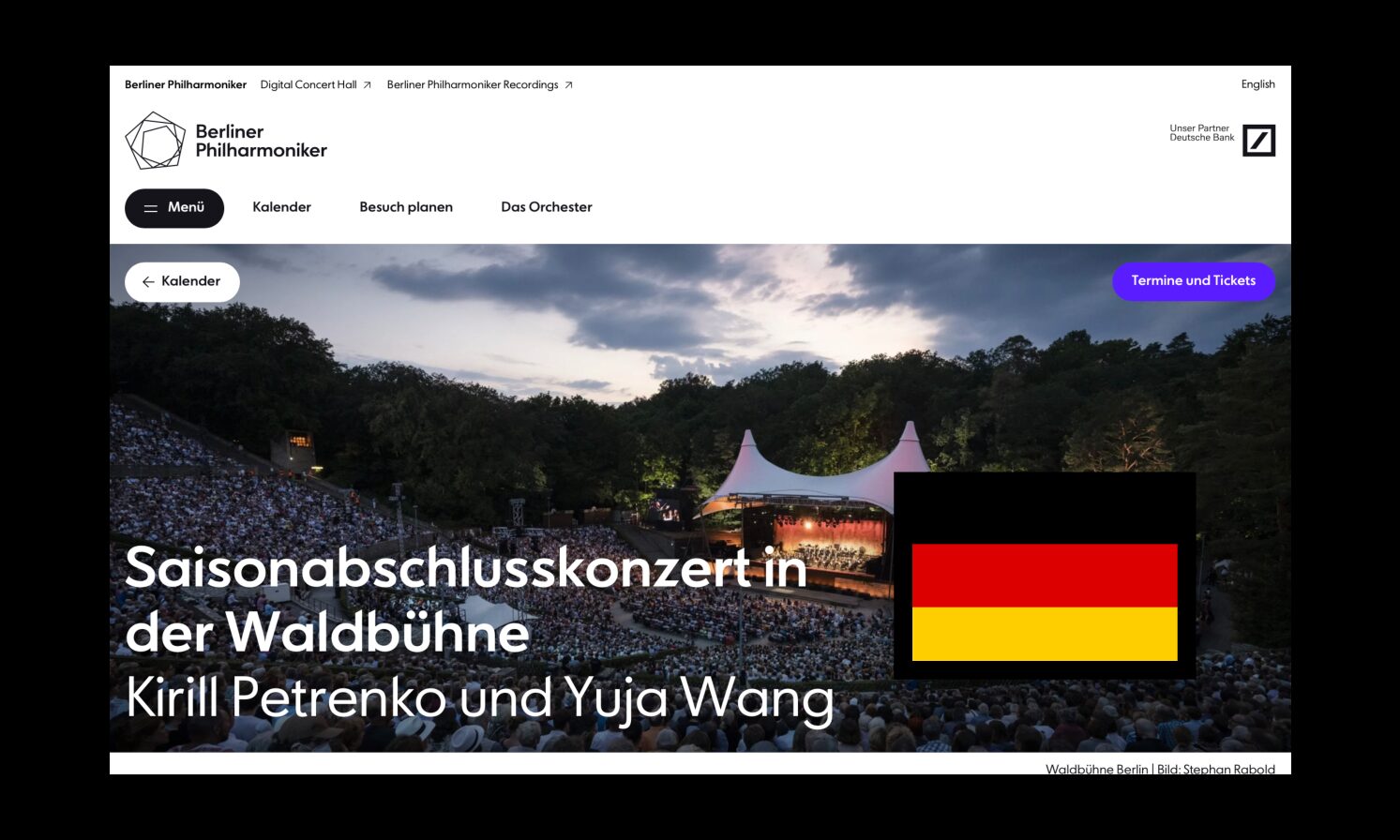戦後、復活したバイロイト音楽祭を率いたのは、音楽祭の創始者リヒャルト・ワーグナーの孫にあたるヴィーラントとヴォルフガングの兄弟だった。時代背景や伝統を超越し抽象化を極めた彼らの演出・舞台は、「新バイロイト様式」と呼ばれ一世を風靡することになる。
しかし、1966年に主に演出を担ってきた兄のヴィーラントが急逝。ヴォルフガングが総監督として重責を一身に担うようになった1970年代以降は、外部の演出家を積極的に招聘する方針に転換。パトリス・シェロー、ゲッツ・フリードリヒ、ハリ—・クプファーといった時代を代表する俊英たちが集結するようになった。彼らは期待に応えて現代社会の矛盾や政治状況などを反映した斬新な舞台を製作、新たな潮流を作り出していった。
今回取り上げる《ローエングリン》は1982年の音楽祭を収録したもので(プレミエは1979年)、フリードリヒの演出だ。音楽祭の映像が我が国でも解禁されるようになったのがこの頃で、今でも多くの方がその貴重な体験を語っているほど。僕も当時、NHK教育テレビで放映されたものを見て、大変感激した記憶がある。かつてPHILIPSからLDでリリースされた豪華な「バイロイト・シリーズ」にも収録されていた。
歌劇《ローエングリン》という作品は元々、物語としては謎だらけの設定で、いくらでも解釈が可能なので、最近では様々な「読み替え」演出が出ている。例えば、エルザがマイホームを夢見て家を建てていたり、主役以外の登場人物は「ねずみ」の衣装を着ていたり、舞台が「学級崩壊状態の小学校」だったり……。
しかし、このフリードリヒの演出はそうしたキッチュな要素は皆無。明暗の対比を基調とした大変緊張度の高いもので、各登場人物の心理的葛藤に重きを置いた重厚な舞台だ。
その時代を代表するヘルデン・テノールだったペーター・ホフマンがタイトルロールを歌っているが、第1幕で彼が舞台奥の光の中から長い金髪姿で登場する場面は非常に美しく、最も舞台映えする瞬間でもある。実際、ロック歌手でもあった彼には、元々浮世離れしたようなところがあり、この配役はまさにぴったり。今聴いても歌・演技・容姿いずれも最高レベルのローエングリンだ。
また、エリザベス・コネルが隅々までよく通る硬質な声で、極めて冷徹なオルトルートを演じていて、ロマンチックに傾きがちなこの作品をきっちりと引き締めている。
さらに演出に寄与しているのは、エルザ役のカラン・アームストロングだ。歴代のエルザに比べると確かに歌は弱いが、ここではまさに彼女以外のエルザは考えられない。人柄の良さとそれゆえの弱さがにじみでているような繊細な演技で、それだからこそテルラムント夫妻につけこまれるという物語の根幹を全身で体現している。
第2幕の幕切れで婚礼のため寺院への階段を上って行くエルザが、いわゆる「禁問の動機」が鳴ると同時に思わずオルトルートを振り返ってしまう場面は、そこに持っていくまでの緻密な演出の流れもあいまって、何度見ても心から震撼させられる。ちなみにこの映像収録の翌年、フリードリヒとアームストロングは結婚することになるのだが、それくらい演出と歌手が一体となって生まれた名舞台・名演出であったということでもある。
指揮はウクライナ生まれで早くから西側で活躍したウォルデマール・ネルソンが担当。祝祭管弦楽団のオケをダイナミックに鳴らしながら、全体を破綻なくまとめている。この後、バイロイトではクプファー演出の《さまよえるオランダ人》も指揮していて、これも映像化されている(1985年収録)。こちらも時代を代表する舞台なので、視聴をお勧めしたい。
amazonでCDを買う ▷
音楽祭プロフィールはこちら ▷
……… アルバム情報
● ワーグナー:『ローエングリン』全曲
ローエングリン:ペーター・ホフマン
エルザ:カラン・アームストロング
オルトルート:エリザベス・コネル
テルラムント:レイフ・ロール
国王ハインリヒ:ジークフリート・フォーゲル
軍令使:ベルント・ヴァイクル
バイロイト祝祭合唱団
ノルベルト・バラチュ(合唱指揮)
バイロイト祝祭管弦楽団
ウォルデマール・ネルソン(指揮)
演出:ゲッツ・フリードリヒ
舞台美術:ギュンター・ユッカー
衣装:フリーダ・パルメジャーニ
収録時期:1982年
収録場所:バイロイト祝祭劇場
録音方式:ステレオ(アナログ/ライヴ)